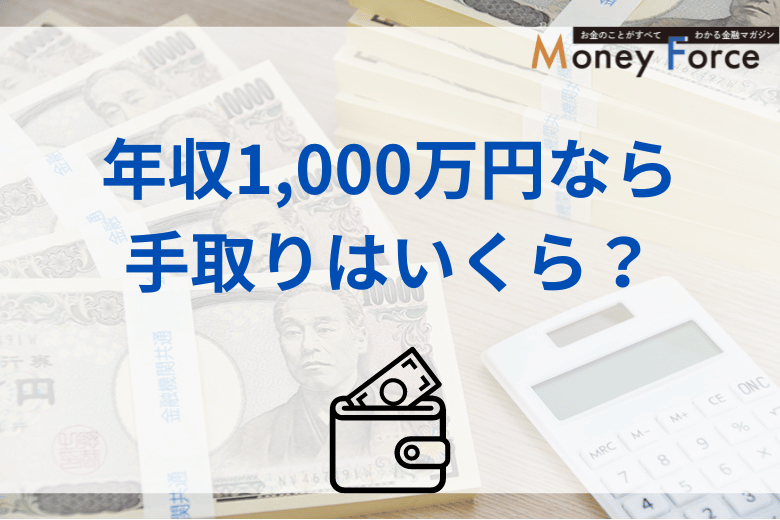
※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。
「生活に余裕がない」
「年収1,000万円くらいあったらもっと裕福な生活ができるのに」
「値段を気にせず好きなものが買いたい」
物価が高騰している近年、こんな風に感じている方は少なくありません。実際収入は多いに越したことはない、と感じている方も多いでしょう。
しばしば高収入として世間から憧れられる、年収1,000万円。平均年収400万円代の現在の日本では、高い水準といえますが、実際のところどうなのでしょうか?憧れの年収1,000万円はどれくらいの割合の方が稼いでいるのか、手取り額や引かれる費用についてご紹介します。
なお家計管理におすすめの無料アプリはマネーフォワードMEです。マネーフォワードMEなら銀行口座とクレジットカード連携で収入と支出が自動で見える化できます。マネーフォワードMEは無料なので、家計を改善したいあなたは以下のボタンよりダウンロードしましょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
【おすすめの保険の見直しサービス】
目次

平均年収が433万円と言われる現在では、年収1,000万円に憧れを抱いている方は少なくないでしょう。平均年収の倍以上を稼いでいるわけなので、裕福に思えるのも無理はありません。
しかし、年収1,000万円という数字が漠然とし過ぎて、稼ぎ方はもちろん生活実態は検討もつかないという方も多いのでは?まずはどんな方が実際に年収1,000万円を稼いでいるのか、見ていきましょう。
年収1,000万円といえば、世間一般的に裕福のスタート地点と捉えられ目標にされやすい収入の代名詞です。高い壁のように感じますが、実際にはどのくらいの方がそれ以上稼いでいるのでしょうか?
国税庁の調査によると、年収1,000万円を超える人の割合は給与所得者の4.6%でした。男性は7.1%、女性は1.1%で、男女間における給与の格差が明確に現れています。(出典:国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査」)社会進出やキャリアアップ化が進んでいるとはいえ、狭き門であることは間違いないでしょう。
国税庁の調査によると、年収1,000万円を超える人の割合は個人事業主ではわずか0.7%でした。事業規模が1,000~4,999人だと7.7%、5,000人超だと8.8%と約10倍に。
さらに、資本金が10億円を超える企業は11.5%もの人が年収1,000万円を超えているそうです。(出典:国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査」)このことから、大企業であればあるほど年収1,000万円超が狙える可能性が高くなることがわかります。
年収は業種や職業によって大きく左右されます。どんな職業でも、年収1,000万円を狙えるというわけではありません。賃金が高い業種は、以下の通りです。
賃金が高い産業
厚生労働省の調査によると、賃金が高いのは電気やガス・熱供給・水道業など生活に欠かせないライフラインに関わる事業です。景気に左右されづらく、給与も安定している業種といって差し支えないでしょう。
また、大企業が多く給与水準が高いことも平均年収が高くなる理由の1つです。憧れの年収1,000万円を目指すなら、賃金が高い職業に就くほうが近道といえそうです。
厚生労働省の統計調査からも分かる通り、それぞれの業種の中でも年代や性別によって収入に差があります。一般的に40代後半から50代前半が収入のピークであり、新卒にあたる20代前半の給与と比べると平均年収は倍以上に。
それでは、新卒採用当初で年収1,000万円を稼ぐことは不可能なのでしょうか。実はそうとは限りません。経済産業省は以下のように発表しています。
NEC AI等の分野で大学時代の論文が高い評価を得た新卒者を対象に、年収1,000万円以上を提示。
DeNA AIシステム部独自の人事制度として、年収600万~1,000万円を可能に。新卒も中途も区別せず適用。
日本ではICT(Information and Communication Technology)人材は量的に不足しており、今後はますます深刻化するといわれています。また量のみならず、質の面でも不足しているとの見方もあり、優秀なデジタル人材の確保に力を入れている企業も。
高度なIT技術を持つ人には、通常よりも高い水準の給与が設定される例も出てきました。新卒であっても、年収1,000万円は夢ではなくなってきています。

憧れの収入の代名詞といわれる年収1,000万円ですが、あくまでも額面上の話です。実際はここからさまざまな費用が引かれるので、年間1,000万円すべてが自由に使えるわけではありません。
そうなると、気になるのは年収1,000万円稼いだらいくら使えるのか、手取りの額です。手取り額までにどんな費用がいくら引かれるのか、詳しく説明するので見てみましょう。
日本では超過累進課税制度が採用されており、年収が上がれば上がるほど多くの税金を支払わなければなりません。また、その他の費用も年収によって金額が異なります。
実際の給与明細を見て、一体何がこんなに引かれているのだろうと疑問に思っている方も多いでしょう。年収から以下のような保険料や税金が控除されたものが手取り額です。
年収から控除される保険料・税金
金額は大きくありませんが、上記以外では雇用保険料も給与から引かれます。
厚生年金とは、会社員や公務員を対象とする公的年金です。事業所単位で加入し、加入が必要か否かは法令で定められています。
保険料は毎月の給与と賞与に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。平成16年から段階的に引き上げられていた保険料率ですが、現在は18.3%で固定。ただし、実際に支払われた給与に保険料率をかけて計算されるわけではなく、標準報酬月額を用いる点に注意が必要です。
月給額がどんなに高くても標準報酬月額は上限の65万円とされ、これに基づいて保険料が徴収されます。給与と賞与の割合によって変わってきますが、年収1,000万円の方の月額給与を84万円・賞与なしと仮定すると最低でも713,700円を支払わなければなりません。
健康保険料は、病気で治療を行う際の医療費の一部を負担するための財源として支払う公的な医療保険料です。正社員や法人役員はもちろん、パートやアルバイトでも要件にあてはまれば対象に。(参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。」)
保険料は厚生年金料と同じく毎月の給与と賞与に保険料率をかけて計算され、事業所と折半します。
全国健康保険協会の場合は、都道府県ごとに異なりますが大体10%前後。(出典:全国健康保険協会「令和4年度都道府県単位保険料率」)健康保険組合の場合は別途確認が必要です。
年収1,000万円の方の月額給与を84万円・賞与なしと仮定すると、年間の保険料は約488,538円となります。
介護保険料は、介護を必要とする高齢者とその家族を社会全体で支えるために支払う保険料です。要介護認定を受けた方が介護サービスを利用する際に自己負担額1〜3割で利用できます。
40歳から加入が義務付けられており、65歳以上で支払い方法が変わりますが一生涯支払わなければなりません。第2号被保険者である40〜64歳までは健康保険料の一部として、65歳以上は原則として年金からの天引きになります。
64歳までの介護保険料は、毎月の給与と賞与に保険料率をかけて事業所と折半です。全国健康保険協会の2022年の介護保険料率は1.64%。
月額給与84万円・賞与なしなら、年間の保険料の負担額は約82,656円です。
ただし、健康組合の場合は異なりますので確認してください。
1年間のすべての所得から所得控除額を差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出するのが所得税です。日本では超過累進課税制度を採用しており、所得が多くなるほど多額の税金を支払わなければなりません。
年収1,000万円であれば課税所得は330万円以上695万円未満となるため、所得税率は20%になります。また、同じ年収1,000万円であっても家族構成や控除額によって、納める所得税に違いがでてきます。
会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整によって正しい税額に精算する仕組みです。
住民税は地方税の一種で、道路や公共施設の整備・福祉・教育などの行政サービスに幅広く使われる税金です。市町村民税と道府県民税があり、各市町村に一括して納めます。
1年間の収入を元に算出されますが、所得税とは違い翌年の6月から1年間で納付する点に注意しましょう。課税額は均等割と所得割の合計で決まりますが、自治体によって均等割の額に違いがあるので注意が必要です。
また、実際の収入ではなく、所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけるため、家族構成や控除額によって税額は異なります。
年収1,000万円は額面上であり、実際にはさまざまな費用が差し引かれます。そのため、年間1,000万円が自由に使えるわけではありません。
日本では超過累進課税制度を採用しており、所得が多くなるほど税額は増え、保険料の支払いも高額になります。家族構成や控除額によって違いはありますが、手取りは一般的に700〜750万円ほどといわれており意外に少なく感じる可能性も。
裕福かどうかは個人的な主観で異なりますが、平均年収に比べると手取り額も多いため十分な収入だといえるでしょう。
関連記事:【年収1,000万円超えの人の貯蓄は?】収入に対する貯蓄割合や金額、さらに貯蓄を増やすコツを紹介
年収1,000万円は憧れの収入の代名詞ともいわれていますが、実際の手取り額は700〜750万円ほどです。所得税や住民税などの税金をはじめ、厚生年金や健康保険・介護保険などの保険料を支払わなければなりません。
家族構成によっては、年収1,000万円でも決して裕福ではないと感じている方もいるでしょう。確かに税金や保険料だけで年間250〜300万円を支払うため、そう感じてしまうのも無理はありません。
しかし、平均年収が433万円といわれている現在、倍以上となる年収1,000万円は理想的な収入であることは間違いないでしょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
【おすすめの保険の見直しサービス】

高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
編集部おすすめ記事
人気記事
編集部おすすめ記事
(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.