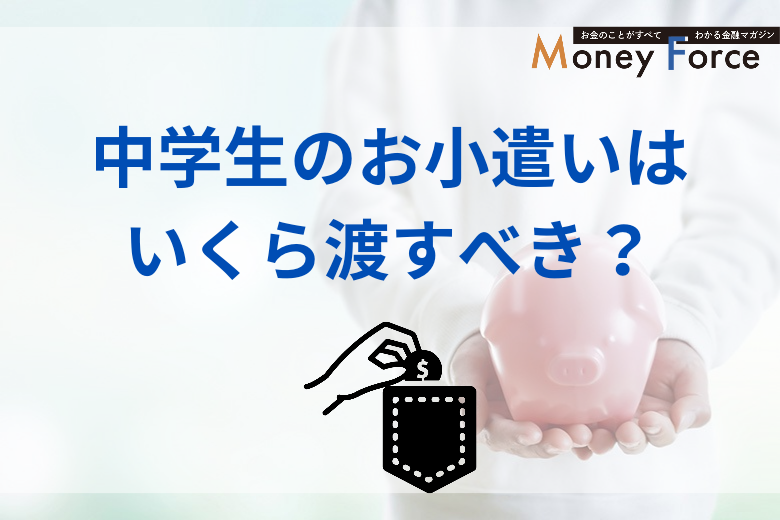
※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。
「中学生にはお小遣いをいくら渡したらいいの?」
「お小遣いはどのタイミングで渡すべき?」
とお悩みではありませんか?
中学生は友達同士での外出も増えてくる時期。お小遣いの金額を考え直す必要があるかもしれません。親としては、せっかくお小遣いを渡すなら、将来のためにお金の適正な使い方を身につけて欲しいところです。
子どものお小遣いで悩むあなたのために、この記事では一般的な中学生のお小遣いの相場や、渡し方のメリット・デメリットを紹介します。世間一般の基準を知り、あなたの家庭に合わせたお小遣いのルールを見つけてみてください。
なお家計管理におすすめの無料アプリはマネーフォワードMEです。マネーフォワードMEなら銀行口座とクレジットカード連携で収入と支出が自動で見える化できます。マネーフォワードMEは無料なので、家計を改善したいあなたは以下のボタンよりダウンロードしましょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
【おすすめの保険の見直しサービス】
目次

まずは、中学生のお小遣いの相場や使い道を知ることから始めていきましょう。中学生は友達付き合いも増えて、お金が必要な場面が増えてくる時期です。
しかし、お小遣いを渡す必要があるとわかっていてもいざ渡すとなると、何を基準にしたらいいかと悩む方も多いでしょう。そこで下記の内容について紹介します。
お小遣いは渡し方も含めて考える必要があるので、金額の相場のあとに紹介します。ぜひ続けて読んでみてください。
まずは、中学生のお小遣いの最頻値・平均値・中央値を見てみましょう。
| 学年 | 最頻値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 中学生 | 1,000円 | 2,536円 | 2,000円 |
出典:金融広報中央委員会『「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査』
もっとも多かった回答は1,000~2,000円未満で、全体の32%でした。なかでも1,000円と答えた家庭が最も多い結果になりました。
平均値・中央値が少し高めなのは、3,000円以上というより多くの金額を渡している家庭があることが理由です。以上のことから中学生のお小遣いは、1,000〜2,000円が一般的な金額であることがわかります。
お小遣いの相場がわかったところで、次に中学生は何にお小遣いを使うのかを見てみましょう。使い道をランキングにしたのが下記の表です。
| 順位 | 中学生(27項目中) |
|---|---|
| 1位 | 友達との外食・軽食代 |
| 2位 | おやつなどの飲食物 |
| 3位 | 友達へのプレゼント |
| 4位 | 文房具 |
| 5位 | 家の人へのプレゼント |
| 6位 | 休日に遊びにいくときの交通費 |
| 7位 | ゲーム代 |
| 8位 | 小説や雑誌 |
| 9位 | まんが |
| 10位 | 映画やライブのチケット |
出典:金融広報中央委員会『「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査』
上位3位に「友達との外食・軽食代」や「友達へのプレゼント」の友達関係が2つもランクインしています。小学生の回答ではおかしやおもちゃが上位でしたが、中学生になると友達づきあいで使うお金が増えてくることがわかります。
中学生は部活動が始まったり、遊びにいく範囲が広ったりする時期です。子どものお小遣いの使い方や使い道により気をつけなければならないともいえるでしょう。

ここまで中学生の話をしてきました。ただ、お小遣いは、小学生や高校生も合わせて流れで考えるのがおすすめです。小学生を基準に年齢とともに少しずつ金額を上げていく家庭もあるでしょう。
そのため、ここでは小学生や高校生のお小遣いの相場を紹介します。高校卒業までのお小遣いのイメージがつくと家計管理もしやすくなるので、この機会で見通しを立ててみましょう。
まずは小学生のお小遣いの一般的な金額からみていきましょう。最頻値と中央値を中心にみていきます。
| 学年 | 最頻値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 低学年 | 500円 | 1,004円 | 500円 |
| 中学年 | 500円 | 864円 | 500円 |
| 高学年 | 500円 | 1,085円 | 1,000円 |
出典:金融広報中央委員会『「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査』
小学生は6年間ありますが、どの学年でも最頻値(もっとも回答が多い金額)は500円になっています。中央値をみても、低学年・中学年は500円、高学年のみ1,000円という結果です。
学年とともに段階的に上げている家庭もあるようですが、500〜1,000円が小学生のお小遣いの相場と考えていいでしょう。
次に、高校生のお小遣いです。どのくらいが一般的なのか、同じように見ていきましょう。
| 学年 | 最頻値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 高校生 | 5,000円 | 5,114円 | 5,000円 |
参照元:金融広報中央委員会『「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査』
最頻値・平均値・中央値の3つの値すべてが、ほぼ5,000円という結果になりました。高校生になると家庭による金額の違いが小さくなり、相場は5,000円とわかりやすいです。
中学生のお小遣いから倍以上の金額になっているのは、それだけ行動範囲や交友関係が広がっているからでしょう。金額が増えると使い道も多様になるため、お小遣い帳などを利用して子ども自身で管理をすることも必要になるかもしれません。

これまで小学生以上の子どもに関してお話ししてきましたが、お小遣いを渡し始める年齢も悩むポイントです。ここでは一般的にはいつ頃からお小遣いを渡し始めているのかを見てみましょう。
おこづかいは、小学生の7割強、中学生の8割強、高校生の約8割が「もらっている」
と回答している
小学生でも7割強の子どもがもらっているとあり、小学生の頃からお小遣いを渡す家庭がほとんどのようです。また、中学生の割合が一番高いこともわかりました。
高校生はアルバイトができますが、中学生はまだアルバイトができない年齢です。そのことも中学生がお小遣いをもらう割合が一番高い原因といえるでしょう。

お小遣いのだいたいの金額や目的・渡し始めている時期がわかったところで、次の問題は渡し方です。子どもがお小遣いを使い過ぎず、計画的にお金を使うことを覚えるためにも、この渡し方は重要な要素。まずは、どのような渡し方があるのかをご紹介します。
お小遣いの渡し方
それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご家庭に合った方法を検討してください。それでは、下記で4種類の渡し方に関して詳細を見ていきましょう。
最も一般的なのが、渡す時期と金額が決まっている「定額制」です。メリットは、渡される日がわかっているため、決められた期間で計画的にお小遣いを使う能力が身につくことが挙げられます。金額が決まっているので、使い過ぎも防げます。
デメリットは、決まった時期にいつももらえることでありがたみが減少すること。また、使い道が事前に決まっていないため、何にお金を使っているのか親が把握できない可能性もあります。お小遣い帳などで管理して親が確認できる状態にするなど工夫をしましょう。
子どもが必要とするタイミングで必要な金額を渡す「都度制」。メリットは、お小遣いの用途を親が把握できる点です。また、お小遣いをもらうために親を納得させなければいけないため、交渉する能力が身につきます。
デメリットは、制限なくあげていると欲しいものがいつでも手に入ると感じて自己抑制能力が下がることです。親の方でもいくら渡しているのか把握できるようにして、渡し過ぎに注意しましょう。
約束した目標を達成した場合やお手伝いをした場合のご褒美として渡す「報酬制」。メリットは、お金をもらうことにハードルがあるため、お金へのありがたみを感じられます。また、決めたことを達成するために努力する能力が育ちます。
デメリットは、あまりにも高い目標を設定しすぎると子どものやる気を失ってしまう可能性があること。さらに、報酬がなければ頑張らないようになるかもしれません。また、お小遣いが足りなくなってもお手伝いをすれば貰えるため、計画性が身に付かないデメリットも。
結果が出ないと報酬を0にするのではなく、頑張ったプロセスを褒めるバランスも必要です。目標のハードルに合わせて、適切な金額を設定しましょう。
1年分など、まとまったお小遣いを一度に渡す「一括制」。メリットは、長期的な計画をたてて自己管理する必要があるため、残高を意識した金銭感覚が養われることが挙げられます。
デメリットは、計画を立てる能力がまだない段階では失敗しやすく、早い時期に使い切ってしまう可能性が。また、計画がうまくいかないと友達づきあいに制限が出てしまい、友達との関係に支障が出ることも懸念点です。
一括制をとる場合は、計画段階や途中経過で大人が確認をするなどの工夫が大切でしょう。成功すれば、長期的な管理能力がつく良い金融教育になります。
この記事では、中学生のお小遣いの相場や使い道、お小遣いの渡し方のメリット・デメリットを紹介しました。最初は子どもにお金を渡すことに不安を感じるかもしれません。しかし、お金は誰もが一生付き合っていく大切なものです。
だからこそ、交友関係が広がりお金が必要になる中学生のタイミングから、お小遣い制で金銭感覚を養っていきたいところ。
お小遣いの渡し方や金額に正解はないので、子どもとも話し合い試行錯誤しながら進めていくことが重要です。ぜひこの記事を参考にご家庭に合ったお小遣いのルールを作ってください。
なお、家計を管理するならマネーフォワードMEがおすすめ。何にいくらつかったかを自動で記録できるのに、なんと無料で使えます。 マネーフォワードMEのダウンロードは以下の公式アプリストアからできます。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
【おすすめの保険の見直しサービス】

高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
編集部おすすめ記事
人気記事
編集部おすすめ記事
(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.