
※この記事は商品プロモーションを含むことがあります。
「生命保険でいう日帰り入院はどんな意味?」
「日帰り入院と通院はどう区別されるの?」
「病院のベッドで休んだのに給付金が受け取れないのはなぜ?」
と悩んでいませんか?
近年は、医療技術の発展により入院日数も減少傾向にあります。いざという時に備えるために加入する医療保険の中には、短期間の入院でも給付金が支給される商品が増えてきました。しかし、どのようなケースが該当するのか、通院との見分け方について正確に把握している人はそう多くはないでしょう。
そこで、日帰り入院とはどのようなケースを指すのか具体例を交えながら、解説していきます。給付金を受け取る条件や請求の流れについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
なお家計管理におすすめの無料アプリはマネーフォワードMEです。マネーフォワードMEなら銀行口座とクレジットカード連携で収入と支出が自動で見える化できます。マネーフォワードMEは無料なので、家計を改善したいあなたは以下のボタンよりダウンロードしましょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
目次
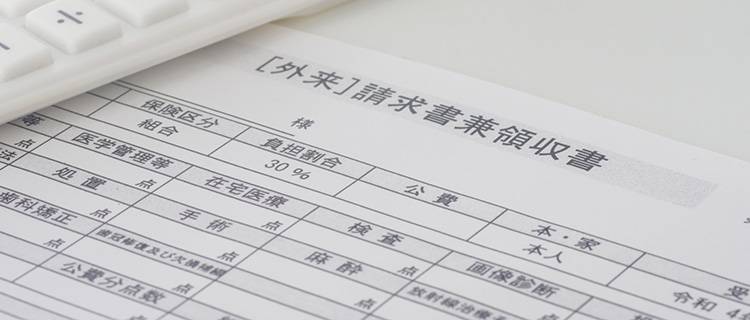
厚生労働省の調査によると、2020年9月に退院した一般病床の患者の70.5%が0~14日で退院していました。(出典:厚生労働省「令和2年(2020)患者調査の概況」)
1996年のデータでは58.2%だったことから、以前に比べると入院期間が短くなっている傾向があることがわかります。(出典:厚生労働省「平成8年患者調査の概況|(2)在院期間」)
その傾向に合わせて、医療保険も短期間の入院から給付の対象となるものが多く出てきています。特に短いものでは日帰り入院から給付金が受け取れますが、日帰り入院とは何なのでしょうか。ここでは、日帰り入院の条件と通院との見分け方について解説します。
日帰り入院の条件
それぞれ詳しくみていきましょう。
日帰り入院は、入院した日と退院した日が同じ日付であることが条件の1つです。入院した時間に関係なく、日付が変わる当日中に退院しなければ該当しません。そのため、23時に入院し翌日の朝10時に退院した場合であっても、入院日数は2日とみなされます。
24時間以内に退院すれば日帰り入院になると勘違いしやすいので注意しましょう。あくまで日付を跨がないことが日帰り入院の条件です。
日帰り入院の場合、病院に滞在する時間が24時間以内となり通院との区別が難しいと感じる方も多いでしょう。判断基準は「入院基本料」の支払いが発生しているかどうかを確認するのが確実です。
医療機関から発行される入院証明書に「入院」の記載があることや領収書の入院料等の欄に、診療報酬点数の記載があるのかを確認しましょう。この部分に点数の記載があれば、通院ではなく入院扱いになります。例え病院への滞在時間が1時間であったとしても、入院料等の欄に点数が載っていれば入院と判断されるのです。

入院日数が減ってきているとはいうものの、実際みんなは何日くらい入院しているのでしょうか。生命保険文化センターが令和元年に過去5年間に入院した人を対象に調査を行いました。その結果を参照してみましょう。
| 年齢 | 5日未満 | 5~7日 | 8~14日 | 15~30日 | 31~60日 | 61日以上 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 20.9% | 27.3% | 27.1% | 15.7% | 5.3% | 3.6% | 15.7日 |
| 20歳代 | 25.0% | 34.4% | 21.9% | 12.5% | 0.0% | 6.3% | 14.4日 |
| 30歳代 | 25.4% | 31.3% | 25.4% | 10.4% | 4.5% | 3.0% | 13.5日 |
| 40歳代 | 25.0% | 32.1% | 24.1% | 12.5% | 4.5% | 1.8% | 12.3日 |
| 50歳代 | 18.9% | 30.3% | 28.0% | 13.6% | 6.1% | 3.0% | 15.2日 |
| 60歳代 | 18.7% | 19.7% | 29.3% | 20.7% | 6.6% | 5.1% | 19.0日 |
出典:生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」
年齢が若いほど入院日数が少なく、年齢とともに入院日数が長くなる傾向があります。そして、全体の20%が5日未満で退院している結果になりました。この中で日帰り入院の割合はわかりませんが、日帰り入院から給付金が受け取れる医療保険に加入する価値はあるでしょう。
また、同資料では入院時の自己負担額も調査しています。5日未満の入院の平均自己負担額は10.1万円という結果に。短期間の入院でも経済的負担は大きいことがわかります。医療保険で備えておくと安心でしょう。

日帰り入院に該当するかどうかは、医師が入院が必要か判断して決定します。病院での滞在時間が長くても、判断によっては入院ではなく外来になってしまう可能性もあります。結局のところケースバイケースですが、それでは自己判断がしづらく悩むでしょう。
そこで、どのような場合が該当するのか自分でも判断できるよう、分かりやすく以下の2つのケースの具体例をご紹介していきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
近年は医療技術の発展により、以前は入院を伴わなければできなかった手術や治療も日帰りで受けられるケースが増えてきました。そのような手術・治療を行った場合は、日帰り入院として扱われることが多くなっています。入院に該当する手術や検査・治療の具体的な例は次の通りです。
検査・治療の具体例
このような治療や手術を行った場合には、入院として扱われるケースが多くなっています。しかし、あくまでも治療後の安静期間の指示や経過観察が必要かどうかを基準に、医師によって判断された場合のみ該当します。上記のような治療や手術を行っただけでは日帰り入院になるとは限らないので、注意してください。また医療保険に加入した時期や内容によっても判断が異なる場合があります。
そもそも入院に対応できるのは、20以上の病床を備える病院と定義される医療機関か、有床診療所のどちらかです。(参照元:厚生労働省)入院設備のない無床の診療所で手術や治療を行ったとしても、通院とみなされ入院とはなりません。
無床診療所では、外来用のベッドしか用意されておらず、入院として扱うことが認められていないためです。また、病院や有床診療所であっても治療や休養のみであれば日帰り入院と認められないため注意しましょう。

近年は入院期間が短くなっている傾向にあり、7割近くの人が入院しても2週間以内に退院しています。そのため現在多くの保険商品において、日帰り入院でも生命保険の給付金を受け取れるようになってきました。
しかし、入院だからといって必ずしも給付金が受け取れるとは限りません。給付金を請求する場合、以下の4つのポイントについて確認しておくことが重要です。
給付金に関する注意点
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
手術には、外来で受ける手術と入院が必要となる手術の2種類が存在します。外来で受けることが可能な手術の場合、日帰り入院にはあたらない可能性があります。また、医師が入院の必要がないと判断した場合も認定されないため注意しましょう。
ただし、入院設備のある病院や有床診療所で手術を受ける場合は、入院を希望すると伝えることで配慮してくれる可能性もあります。
日帰り入院と認定されたとしても、必ずしも給付金が受け取れるとは限りません。なぜなら給付金が適用されるかどうかは、加入している保険商品次第だからです。
特に従来の医療保険では、入院期間を限定した免責期間が設けられた商品が一般的でした。具体的には5日以上の入院で支給するといったものです。なかには10日以上入院すると1日目からの給付金が受け取れるものもありますが、その場合は入院期間が9日以下であれば支給されません。
あなたが加入している保険ではどのような条件が設定されているのか、しっかり確認してください。
日帰り入院をした場合、給付金を受け取るためには、保険会社へ請求手続きを行わなければなりません。その際に必要となるのが、給付金請求書や領収書・診療明細書・退院証明書・診断書などです。必ずしもすべてを揃えないといけない訳ではありません。
請求に必要となる書類は保険商品によって異なるため、自己判断せずきちんと確認を取るようにしましょう。特に診断書の作成には、数千円程度の手数料がかかる可能性があります。一定の要件を満たせば医療費の領収書で代用できることもあるので、事前に確認しておいてください。
日帰り入院による給付金の請求には、ほとんどの保険商品において期限が設けられています。保険会社や商品によって異なりますが、支払事由が生じた日の翌日から数えて3年以内に設定されている場合がほとんどです。(参照元:生命保険文化センター)
一定の条件を満たせば申請期限を過ぎても給付金を請求できるケースもありますが、早く行っておくことに越したことはありません。入院給付金を請求する場合は、退院後早めに必要書類を取得し申請しましょう。
なお家計管理におすすめの無料アプリはマネーフォワードMEです。マネーフォワードMEなら銀行口座とクレジットカード連携で収入と支出が自動で見える化できます。マネーフォワードMEは無料なので、家計を改善したいあなたは以下のボタンよりダウンロードしましょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化
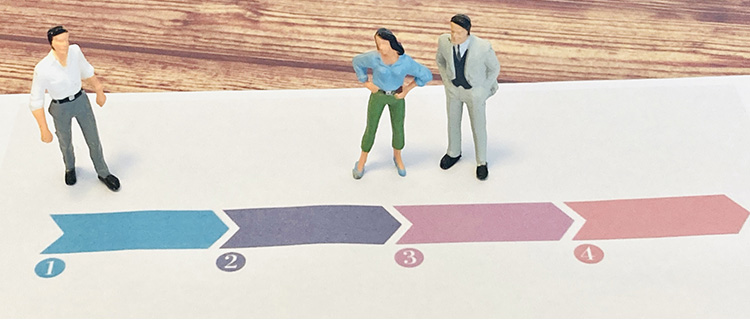
つぎは手続きについて着目してみましょう。入院給付金を請求したことのない人は、どのような流れで申請を行うのか不安に思うかもしれません。事前に確認しておくことで無駄を省けるだけでなく、ゆとりを持って請求できます。入院から請求までの流れは、以下の通りです。
請求までの流れ
手術や治療を受けた場合には、まず医療機関に入院にあたるのかを問い合わせましょう。外来で治療や手術を受ける場合は、給付金の対象とはなりません。
また、日帰り入院であっても給付金が支給されないケースもあるため、保険会社へ給付対象になるかを確認する必要があります。医療機関と保険会社の双方に日帰り入院と認められた場合は申請期限内に手続きが必要なので、必要書類等も確認しておいてください。

保険商品は多数存在し、給付金が支給される条件もさまざまです。特に従来の医療保険では免責期間が設けられている商品が多く、1日だけの入院では給付金が受け取れない可能性もあります。
しかし、近年は医療技術の進歩により、入院日数は年々減少しています。以前は入院が必要だった手術も日帰りで行えるようになっており、今後も日帰り入院は増えていくことが予想されるでしょう。
ただし、日額タイプで支給される保険の場合、給付金額は少額になるので診断書が必要なケースでは相殺されてしまう可能性も。入院一時金のついた保険商品なら、1日の入院でもまとまった額の給付金が受け取れます。今後医療保険を選ぶ際は、入院一時金のある商品を選ぶと良いでしょう。
入院と退院が同日に行われる入院のことを日帰り入院といいます。医師が入院が必要と判断した場合のみで、外来で手術や治療を受けた場合は該当しません。該当すれば医療保険の給付金対象となりますが、商品によっては支払い対象外となることもあるため注意が必要です。加入している保険会社に給付金対象となるかどうか、事前に確認しておくようにしましょう。
日帰り入院の場合、給付金額は少額であることがほとんどです。診断書代と相殺されてしまうこともあるため、今後医療保険に加入する場合は入院一時金が付帯するものを検討してみてください。
なお家計管理におすすめの無料アプリはマネーフォワードMEです。マネーフォワードMEなら銀行口座とクレジットカード連携で収入と支出が自動で見える化できます。マネーフォワードMEは無料なので、家計を改善したいあなたは以下のボタンよりダウンロードしましょう。
毎日のお金の出入りを自動で見える化

高柳政道
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
静岡県出身。小売業やメーカー営業を経験後にライターへ転身。 FP資格を活かして執筆業務を行う。 得意分野は「株式投資」「保険」「クレジットカード」「カードローン」など。 保有資格は「CFP」「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」。
編集部おすすめ記事
人気記事
編集部おすすめ記事
(C) 2022- Money Force by TFP Group.inc.